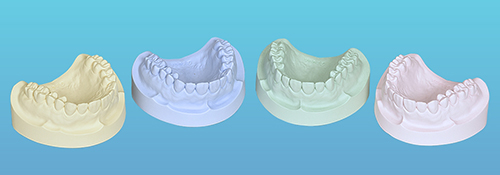私たちが目にする「せっこう」は2分子の結晶水をもつ硫酸カルシウムで、通常「二水(にすい)せっこう」と言います。
・二水せっこうは120℃~150℃に加熱すると結晶水全体の3/2を失って「焼せっこう」になります。
・「焼せっこう」に水を加えると水和反応を起こし、再び元の「二水せっこう」に戻っ て固まります。
チョークを製造するにはこの性質を利用し、金属の型に水と「焼せっこう」を混ぜたものを流し込み、化学反応で固まった後、型から抜き出して製品にします。
下の化学反応式では右から左へいく化学反応になります。チョークの成分は「二水せっこう」です。